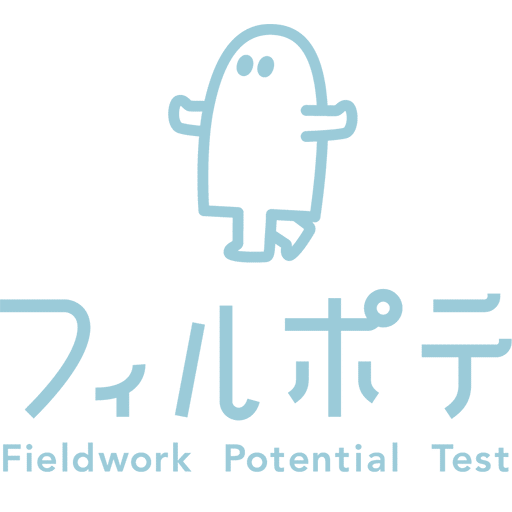柴山です。年齢を重ねると塩分の多い食事を好むようになります。そのメカニズムをお伝えします。
味覚の重要性
・食料や飲料が飲食できるかどうかを判断する
・人間にとっては料理を味わう上で楽しみの一つ
味覚のメカニズム
人間は味覚を舌で感じることが多く、舌の表面にある味蕾(みらい)と呼ばれる感覚器官で感じ取っています
味蕾の中には数十〜数百個の味細胞が集まっていて、その寿命は10日前後と短い期間で新しく入れ替わっています。味細胞は一方の端で味物質受容し、もう一方は神経に繋がっていて味の情報を脳に伝えています。
5基本味(きほんみ)と呈味(ていみ)物質
人間が舌で感じ取ることができる味覚は
甘味(かんみ)・塩味(えんみ)・酸味(さんみ)・苦味(にがみ)・旨味(うまみ)の5種類程度しかないといわれ、5基本味もしくは5味と呼ばれています。
味覚は呈味(ていみ)物質(水や唾液などに溶けて味を感じさせる物質のこと)によってもたらされることが多いです。
基本味と主な主な呈味物質は以下の通りです。
甘味:ショ糖やブドウ糖、果糖
塩味:食塩
酸味:酢酸やリンゴ酸、クエン酸、乳酸
苦味:リモネイド、カフェイン
旨味:グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸
塩味を感じるのは、やはり食塩です。
味の相乗効果
複数の味覚が合わさると味覚が高まることがあり、これを味の相乗効果といいます。昆布と鰹節を合わせる「合わせ出汁」が良い例です。
味の抑制効果
ある味覚が別の味覚を打ち消すこともあり、これを味の抑制効果といいます。コーヒーに砂糖を入れるとコーヒーの苦味が感じられにくくなることが良い例です。
中高年が最も感度の低下を自覚しやすいのは塩味
中高年になるにつれて少しずつ味がわかりにくくなります。
5つの味覚のなかでもっとも感度の低下を自覚しやすいのは塩味です。塩味の感度が低下すると・・・
・味噌汁などの味に物足りなさを覚える
・塩味をつけすぎてもしょっぱさを感じにくい
・ついつい塩をたくさん使ってしまう
食塩の取りすぎは高血圧をはじめとした生活習慣病に深く関わるので要注意です
加齢による味覚の変化の原因
・舌の表面にある味蕾(みらい)の中に多く存在する「味細胞(みさいぼう)」がうまく再生されなくなったり、働きが悪くなる→味覚障害
・キャッチした味の情報を処理する脳の機能が弱くなる →味覚に歪み
・味細胞自体が老化したり傷つく、ドライマウスや厚い舌苔(ぜったい)→味覚障害の原因
・細胞の再生には亜鉛が欠かせないため、血液中の亜鉛が不足→味覚障害の最も大きな原因
亜鉛不足の原因
・加齢により吸収や消化機能が衰えると、摂取しても体外に排出されてしまう
・加齢による体の変化や薬剤の服用
・他の全身疾患などで亜鉛の吸収が阻害、また排泄が促進されやすい
亜鉛は、健康維持に欠かせない必須ミネラルの一つですが、そもそも日本人に食生活は亜鉛が不足しがちです。
亜鉛で味覚障害予防
味覚の重要性で「人間にとっては料理を味わう上で楽しみの一つ」と書きましたが、味覚障害になると、食べること自体が苦痛になる可能性もあり、深刻な事態をもたらします。
亜鉛は、魚介類の牡蠣やうなぎをはじめ、ごま・海藻・大豆・卵黄・アーモンドなどに多く含まれています。
食品の中でトップクラスに亜鉛の含有量の多い牡蠣は可食部100gあたり亜鉛含有量が約14mgのため5〜7個ほどが目安になります。
また、牛肉や鶏肉などの動物性タンパク質と一緒に食べると亜鉛の吸収率が上がります。果物や野菜に含まれるビタミンC には、摂取した亜鉛の働きを高める効果があります。
厚生労働省が定める1日に必要な亜鉛摂取量は成人男性では12mg、成人女性では9mgですが、高齢者はうまく吸収することができないため、この量より多く摂取する必要があります。