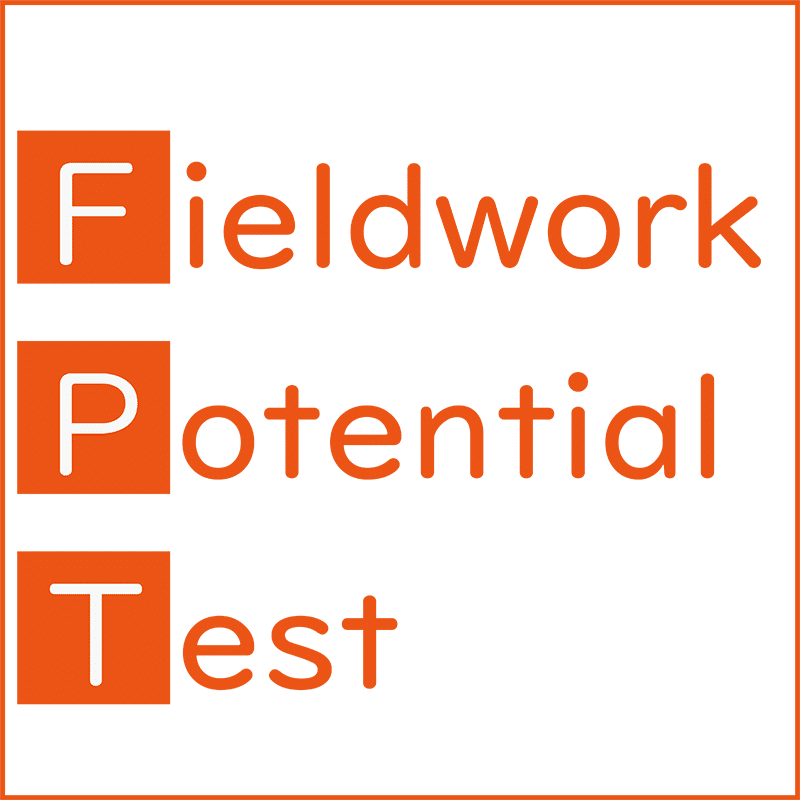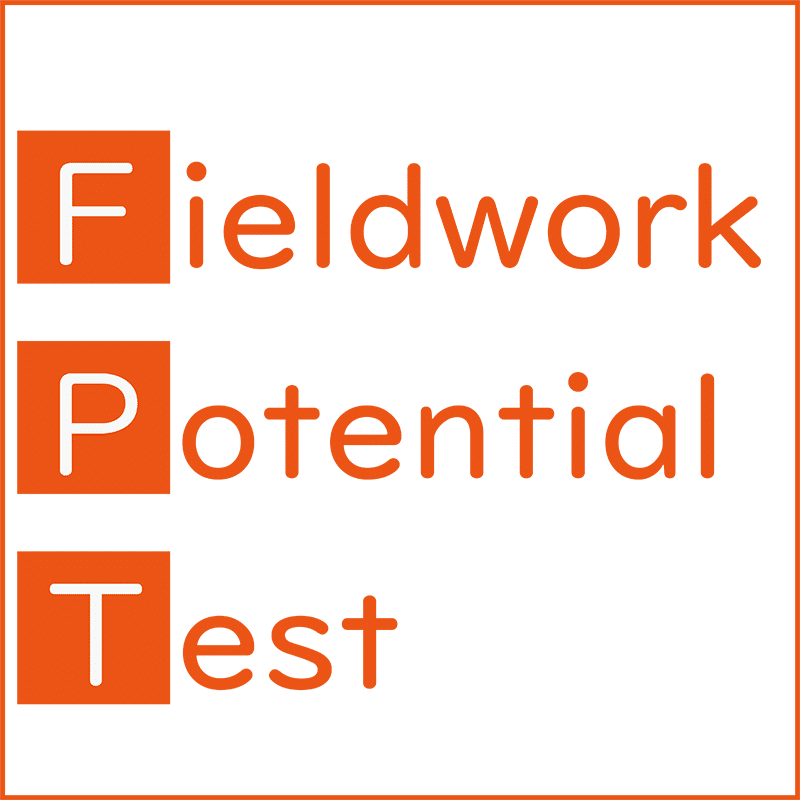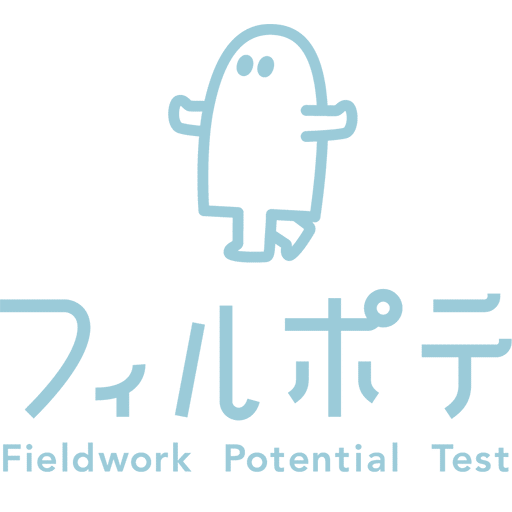柴山です。前回に引き続き今回も免疫についてお伝えさせて頂きます。
免疫細胞とは何か
免疫には「自然免疫」と「獲得免疫」という2つの種類があることをご存じでしょうか?
「自然免疫」は体内に異物が侵入したときに最初にはたらくもので、「獲得免疫」は自然免疫で対処しきれなかった場合にはたらくものです。
2つの免疫には異なる特徴があり、さまざまな免疫細胞がかかわっています。
自然免疫
人間の体にもともと備わっている免疫システムで、体に異常が侵入してきた際に最初にはたらきます。自然免疫には体内に侵入した異物を見つけ、異物のみを攻撃する作用があります。ヒトの細胞にはない特徴を持っている物質を異物だと見分け、体に入り込んできた異物にすぐに対処できるよう自然免疫の機能は獲得免疫に比べシンプルなものです。 自然免疫を担う主な免疫細胞は、異物を食べてから自らが持つ消化酵素などで殺菌・分解をすることができる「貪食細胞(どんしょくさいぼう)」と呼ばれる細胞です。
自然免疫にかかわる主な免疫細胞
①好中球
②マクロファージ(単球)
③樹状細胞
④NK細胞(ナチュラルキラー細胞)
⑤マスト細胞(肥満細胞)
①好中球
好中球は自然免疫を担う代表的な免疫細胞です。
白血球全体の約45~75%程度を占めており、主に細菌などの感染から身体を守ります。貪食細胞の一つで異物を除去する力が強く、感染が起きるとすぐに動員されます。
②マクロファージ(単球)
マクロファージも貪食細胞で白血球の成分の一つです。
白血球の約3~8%を占めており、血管内に存在しているときは単球と呼ばれていますが、血管の外へ移動するとマクロファージという名前に変わります。
マクロファージは異物を取り込んで消化すると、その一部を「抗原」として他の免疫細胞に提示しています。そのため、自分の仲間である他の免疫細胞に敵を知らせるような役割を持っています。
抗原とは
細菌やウイルスなどの病原体、花粉などの他の生物が持つ有機物といった外部から侵入した異物が持つ免疫反応を引き起こす物質のことです。たんぱく質や糖、脂質のほかさまざまな物質が含まれます。
③樹状細胞
樹状細胞も異物を攻撃する作用を持つ貪食細胞の一種で、樹の枝のような突起を持つことが特徴です。血液によって全身に運ばれるため、さまざまな組織や器官に存在しています。
またマクロファージと同じように、樹状細胞は異物を取り込んで消化することでできた物質を抗原として示す役割も担っています。
④NK細胞(ナチュラルキラー細胞)
がん細胞やウイルスなどに感染した細胞を攻撃するのがNK細胞(ナチュラルキラー細胞)です。
他の免疫細胞に抗原を提示されなくても、がん細胞や感染した細胞にアプローチすることができるのがNK細胞の特徴です。
また、NK細胞はリンパ球と呼ばれる細胞の一種で、人の体に生まれつき備わっています。
リンパ球とは
白血球の成分の一つです。NK細胞以外にもT細胞やB細胞といった免疫に関わる細胞が含まれています。リンパ球のうち、NK細胞が占める割合はわずか数%程度です。
⑤マスト細胞(肥満細胞)
マスト細胞は気管支や鼻の粘膜、皮膚などの外部と接触する組織に広く存在している免疫細胞です。肥満細胞と呼ばれていますが、肥満とはとくに関係ありません。
マスト細胞は白血球の一種で、食べ物などから体内に入り込んだ寄生虫から身体を守るはたらきをしています。
獲得免疫
自然免疫で対処しきれない場合にはたらくのが獲得免疫です。
獲得免疫は自然免疫では攻撃できない小さな異物や、細胞に入り込んでしまった異物を取り除きます。獲得免疫は自然免疫よりも侵入してきた異物の特徴をさらに細かく見分けることができます。また、体内に侵入した異物を記憶できるのも獲得免疫の特徴の一つです。
同じ異物が入り込んできたときは、最初のときよりも迅速に異物へ対処することが可能になります。
「免疫がついた」=「同じ病気にかからない」ということではなく、一度侵入してきた異物には速やかに対処することができるため、体内に入り込んでも症状が現れる前に異物を除去できます。この現象は「免疫記憶」と呼ばれています。
獲得免疫にかかわる主な免疫細胞
①T細胞
②B細胞
①T細胞
T細胞はリンパ球の一種でマクロファージや樹状細胞から受け取った抗原の情報をもとに異物を攻撃するはたらきがあります。T細胞は大きく「ヘルパーT細胞」と「キラーT細胞」の2つに分けられます。
ヘルパーT細胞はマクロファージや樹状細胞から提示された抗原の情報に基づき、異物に対する攻撃の戦略を立て他の免疫細胞へ指令を出します。一方キラーT細胞は異物に感染した細胞を見つけ出し直接攻撃を行います。
②B細胞
B細胞もリンパ球の一種です。B細胞はヘルパーT細胞の指令を受けて抗体を作ります。
ヘルパーT細胞はマクロファージや樹上細胞に提示された抗原の情報から、異物への攻撃の戦略を立てる役割を持っています。そのヘルパーT細胞の指令に基づいて、抗原と結合する抗体を作るのがB細胞の役割なのです。 また、B細胞は免疫記憶にも関わっています。最初に抗体を作る際に、B細胞の一部は免疫記憶細胞として体内に長く保存されます。同じ異物が二度目に侵入したときは、免疫記憶細胞となったB細胞が素早く抗体を作り出して異物を攻撃します。
抗体とは
特定の異物にある抗原と結合して、その異物を体内から取り除く分子のことです。免疫グロブリンと呼ばれるたんぱく質からできています。
今回は免疫細胞についてお話させて頂きました。
免疫細胞を知ることで体の仕組みに興味を持っていただければ嬉しいです。
次回は免疫機能を維持するポイントをお伝えさせて頂きます。