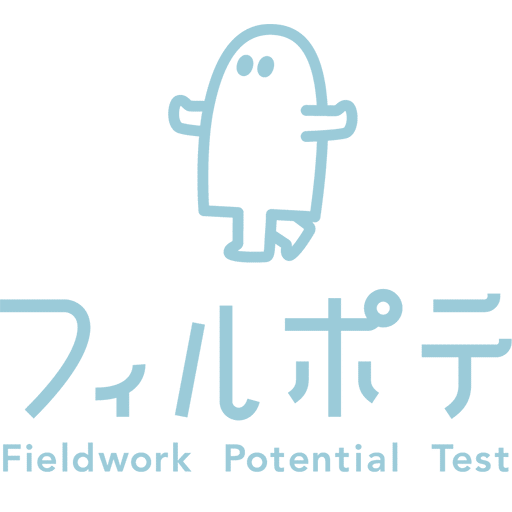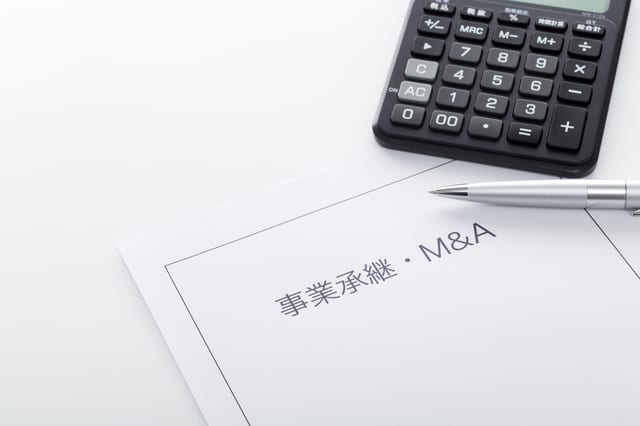福岡です。M&Aは守秘義務などがあり、実体験に触れる機会も少ないので、「とにかくわからない」という印象かと思います。それぞれの立場で起こることを書いていきます。今回は売り手側の準備です。
M&Aのプロセスは結婚に似ている
中小企業M&A成約までのプロセスは、「準備」、「マッチング」、「交渉・契約」
の3つに分けることができます。M&Aは結婚に似ており、結婚に例えるとわかりやすいと思います。
相手を探したり、アドバイスをするM&A専門会社が結婚相談所のようなイメージですね。
「準備」はプロフィールを作成したり、写真撮影したり、相手の希望条件を考えたり、そんな感じです。
「マッチング」は、実際に相手を探す段階です。いろいろな方とデートしたり食事したりしながら自分の理想の相手を探しますよね。M&Aの場合も同じで、この段階で複数社と面談を重ねることが一般的です。
最後に「交渉・契約」ですが、この段階が真剣交際、入籍、結婚式のイメージです。
日本では二股は非難殺到ですね。M&Aも同様で、この段階では相手企業を1社に絞り込み、契約に向けて色々と調査をします。結婚に向けて相手の両親や友人に会ったり、または同棲してみたり、そんな感じですね。
かなりざっくりですが、大体このような流れです。
また、手数料が発生するタイミングについて、図では代表的な手数料を記載していますが各M&A専門会社によって異なります。手数料についてはまた別の機会に詳しく説明させていただきます。


ここからは売り手の「準備」段階にしておくべきことを説明をさせていただきます。
売り手の準備 ノンネームシートと企業概要書の作成
①「自身の考えを整理」、②「自社の強み、アピールポイントを整理」、③「論点の洗い出し」をしっかりした上で、
ノンネームシート(買い手の初期的関心を探るために使用する、売り手が特定されない程度の情報を記載した資料)や
企業概要書を作成する必要があります。
売り手の準備 オーナー自身の考えを整理する
「譲渡の理由」
「譲渡の条件(譲れない条件)」
「譲渡後の方針」
まずはこの3点について深く考えて整理いただきたいです。これらが明確でないと今後の買い手との交渉で真意がうまく伝わないこともありますし、自信を持ってM&Aのプロセスを進めていけないと思います。
また、M&Aのプロセスが進む中で、「本当に譲渡していいのか」と考え悩む瞬間が必ず来ます。そのときに、なぜ譲渡を検討し始めたのか、原点に立ち返る意味でも非常に有効です。
売り手の準備 自社の強み・アピールポイントを整理する
「御社の強みはどこでしょうか?」と聞かれた場合、どのように回答するでしょうか。
買い手目線でいうとM&Aは投資の一種です。1億円で譲り受けるのであれば、将来1億円以上回収したい、そう考えます。したがって、今後も売上が安定して出るだろうと買い手に思ってもらうことが重要です。売上に直接的に繋がる内容をアピールするのがいいと思います。
「社員たちはやりがいをもって長い間辞めることなく働いてくれている。社員は熱意をもって商品開発を進め、数々のヒット商品が生まれた。」この事例の場合、「商品開発力」を一番に推すべきでしょう。
「社員がやりがいを持って働いていること」を一番アピールしたいという社長もいらっしゃるかもしれません。社長として社員をアピールしたい気持ちは自然ですし、採用活用であればそれを前面にアピールすべきだと思います。ただ、M&Aの場合は売上により直結する商品開発力をまずアピールすべきです。
「売上の源泉は商品開発力で、その背景には社員の素晴らしい努力がある」、このような順序で理解してもらった方が買い手は検討しやすいです。
論点の洗い出し
「論点の洗い出し」というと、ネガティブに感じる方もいらっしゃると思います。しかし、M&Aで譲渡することを念頭に長年経営されている方はほぼいないと思いますので、M&A特有の論点があるのは当たり前です。論点がない会社の方がむしろ不自然です!
例えば、取引先との契約で「オーナーが変わるときは事前に許可を取ってください」という条項があることがあります。この条項が一番の得意先との契約にあったとしてもM&Aをしなければ何の問題にもなりませんが、M&Aをする場合は対応方法を検討する必要があります。
事前に論点の洗い出しをしておくことはその後のスムーズな交渉に繋がります!
決算書のみで行う株価試算はあくまで参考程度
最近、「決算書提出いただければ無料で株価試算します!」というM&A仲介会社が多くありますが、100%鵜吞みにしない方がいいです。その株価試算が間違っているというわけではなく、M&Aの価格は買い手によって変わることがあるので、決算書の数値のみで実際のM&Aの価格を出すのは難しいということです。参考指標とするのはいいですが、「その価格で必ず決まる」とは考えないでいただきたいです。
一つ事例を記載します。単純化するため極端な例にしていますが、ご了承ください。
売り手:コーヒー店を経営。コーヒーのみ取り扱い。すごく評判のいいコーヒー。
買い手A:ケーキ屋を経営。ケーキのみ取り扱い。
買い手B:建設業。社長がコーヒー大好きでコーヒー店を経営したいと考えている。
買い手Aと買い手B、それぞれが考える売り手企業の価値は一緒でしょうか?結論、買い手Aの方が高い価格を出せる可能性が高いです。買い手Aのケーキ屋で売り手のコーヒーを販売すれば、売れそうですよね。ケーキとコーヒーは相性いいですし、2社協力すれば売上が上がりそうだから少し高い価格でも譲受したい!こう考えることができます。
一方、買い手Bの場合は建設業で、仕事上でコーヒーと直接繋がりはないので、買い手Aほどの価格は出しにくいと思います。
事例の買い手Aのケースのように、相乗効果によって1+1=2.5のようなことが起こり、それが価格に反映されることがあります。ですので、売り手の決算書の数値だけで実際の価格を出すのは難しいのです。
少し話がずれますが、先ほどの事例で、買い手Aが高い価格を出せるので買い手Aに譲るのが正解、という訳ではありません。売り手オーナーの価値観、考え方次第でどちらも正解だと思います。
将来豊かに暮らしたいので少しでも価格が高い先に譲りたい、そう考えるなら買い手Aが良さそうで、
熱意を持ってコーヒーに向き合ってくれる、とにかくコーヒー愛がある先に譲りたい、そう考えるなら買い手Bが良いかもしれません。
次回は、買い手の準備段階の話をしたいと思います。