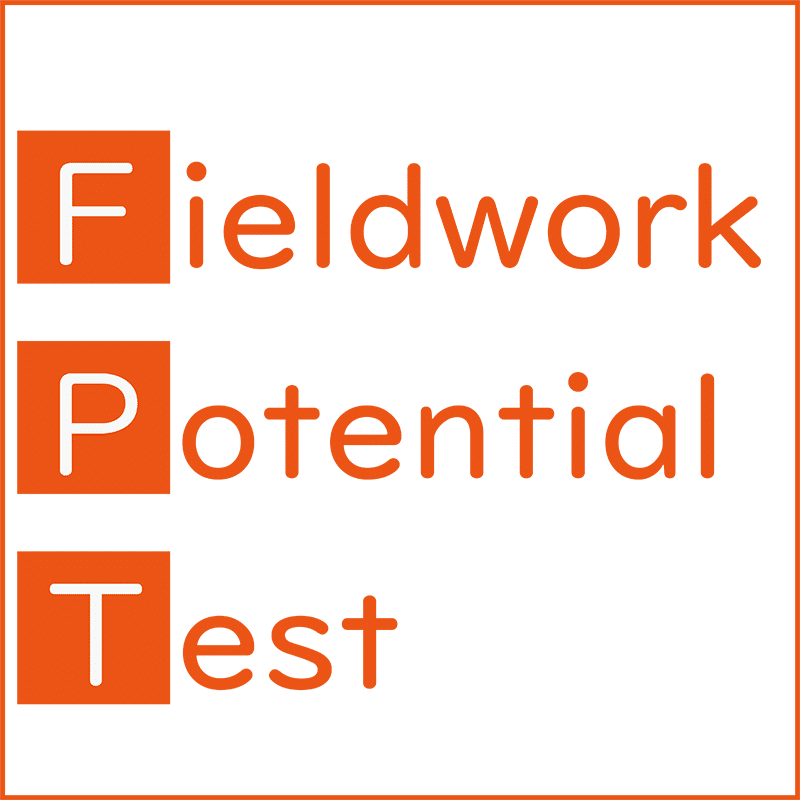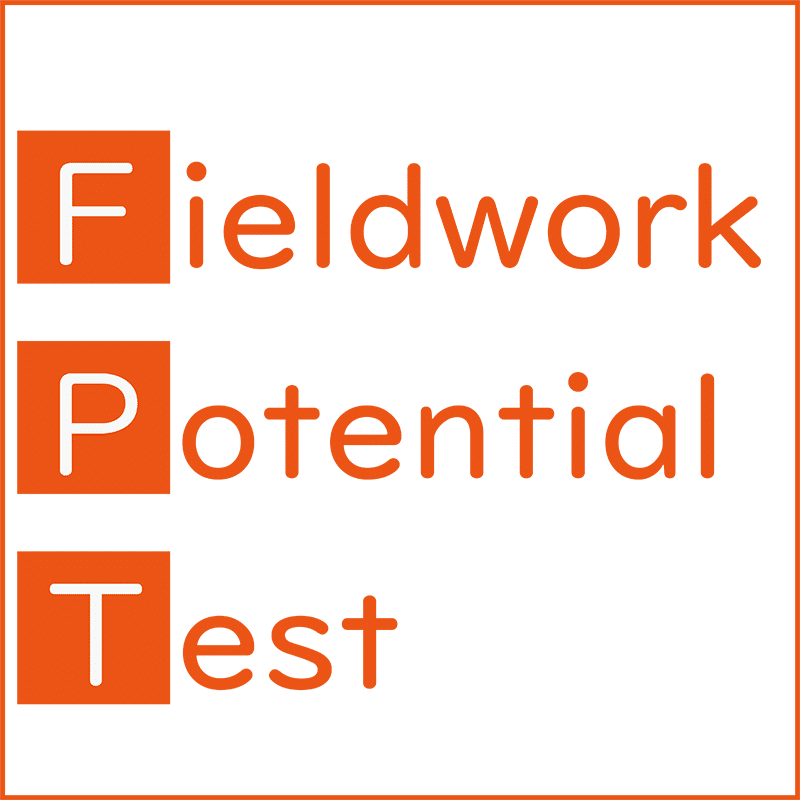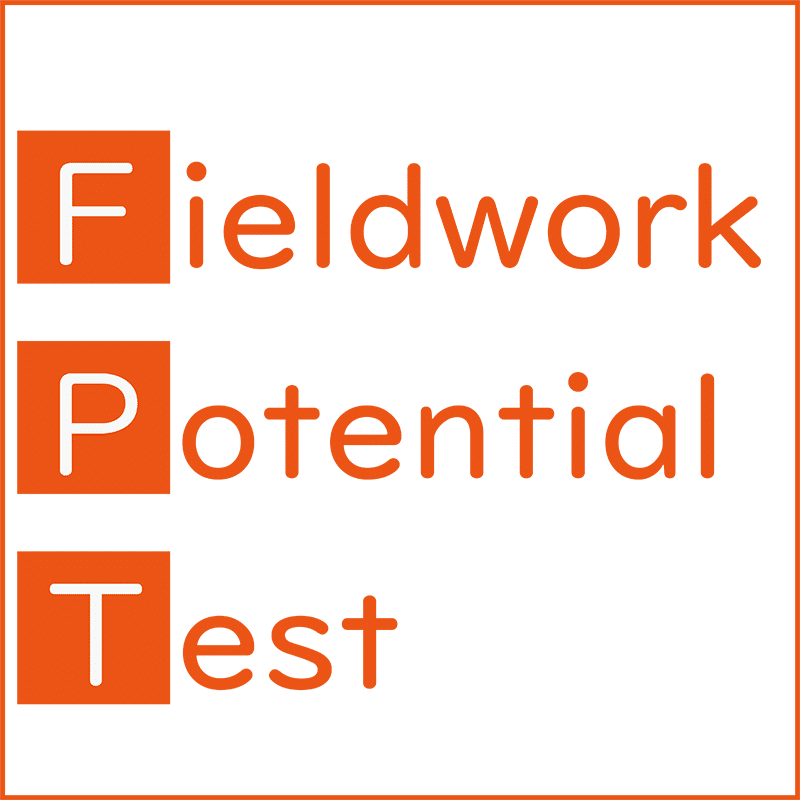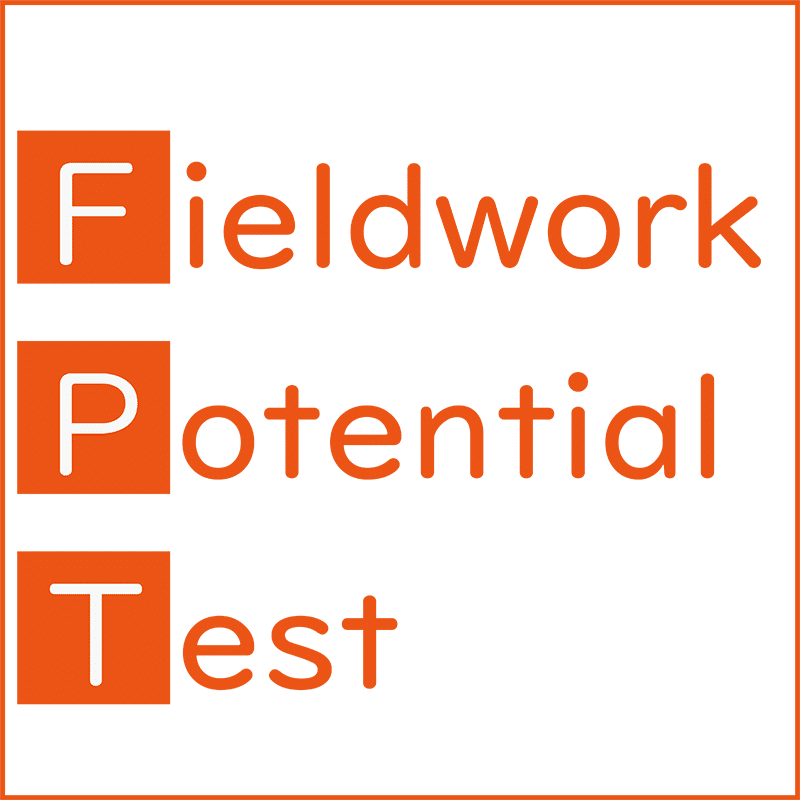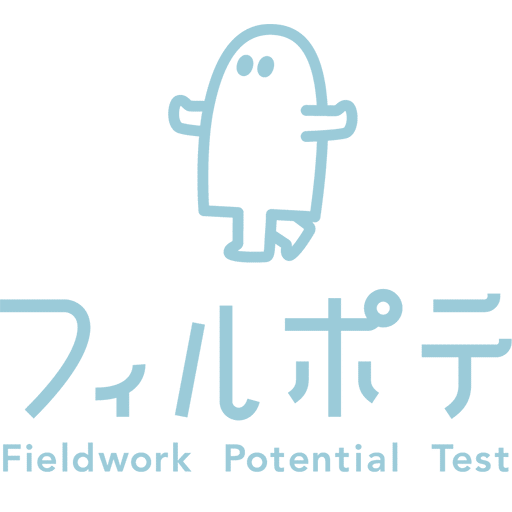前回に引き続き、今回も腸内環境についてお伝えさせて頂きます。
腸内環境を整えることで、免疫力が上がる・代謝が上がり太りにくくなるなど体にとってメリットがあります。反対に腸内環境が悪くなり、腸内細菌のバランスが崩れてしまうと、下痢や便秘、腹痛、免疫力の低下などが起こります。
腸は「第二の脳」と言われるくらい大切な器官です。
今回は腸内環境の整え方についてお伝えさせて頂きます。
腸内環境を整える方法
1:食事
2:運動
3:睡眠
主にこの3つを整えていくと腸内環境が改善されていきます。
1食事
腸内環境を整える食品はたくさんあります。
良く知られているヨーグルトのほか、発酵食品、海藻や野菜・果物、大豆製品、チーズなどが挙げられます。食事だけでなくおやつにも、この中の食品を活用できると腸内環境が整いやすくなります。
ヨーグルト
乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌を食品で摂ることができるので、腸内フローラのバランスを整えて腸内環境を改善することができます。 最近では、さまざまな機能性を持った菌種で発酵したヨーグルトがあるため、自分の目的にあったものを選んでみると良いです。
海藻類
わかめ、寒天などの海藻類は、食物繊維が豊富です。
海藻類の特徴は、水に溶ける「水溶性食物繊維」と、水に溶けない「不溶性食物繊維」を両方含んでいることです。
水溶性食物繊維は、大腸のビフィズス菌や酪酸菌などの善玉菌のエサになる他、ミネラルの吸収をよくしたり、食物の消化吸収を穏やかにする作用があります。
不溶性食物繊維は、便を送り出す腸のぜん動運動を促す作用のほか、便の量を増やす作用も持っています。
便秘の場合は不溶性食物繊維だけを摂ると、逆に悪化する場合があります。また水溶性食物繊維だけ摂ると下痢をする場合がありますが、海藻は2種類の食物繊維を含んでいるので、腸内環境を整えるのに最適です。
キムチ
白菜やきゅうりなどを発酵させたキムチは、生きて腸まで届く乳酸菌が豊富です。食物繊維も摂れるため、腸内環境改善に期待できます。
ただし、あまりに辛いものは胃腸の刺激になるので注意が必要です。
納豆
納豆に含まれる納豆菌は、元々土壌に含まれる枯草菌の仲間で、腸内環境の改善に役立ちます。
大豆のタンパク質やイソフラボンも摂れるので、とても栄養価の高い食品です。大豆に含まれる食物繊維は、腸内細菌のエサになりやすい種類です。
腸内環境を整えるなら、キムチやめかぶなどの食材と組み合わせるとなおよいです。
ぬか漬け
ぬか漬けには植物性の乳酸菌や酵母が含まれています。発酵によりビタミン類やミネラル類も増えるため、生野菜よりも栄養価がアップできるといわれます。 毎食、少しずついただくのがおすすめです。
味噌
大豆を発酵させて作る味噌には、麹菌や酵母菌、乳酸菌などが含まれており、腸内環境を整える作用があります。
特に、味噌汁は発酵食品の味噌と、食物繊維豊富な野菜やキノコ類を掛け合わせて作る最強の腸内環境改善メニューです。毎朝1杯のお味噌汁は腸活におすすめです。
塩麹や醤油麹
発酵食品を食べるのはもちろん、調味料も発酵調味料にすると、腸内環境を整える作用がよりアップします。
塩の代わりに塩麹、醤油麹を使うだけなので手軽に使えます。ドレッシングの味付けにも塩麹や醤油麹を使って作れば、発酵メニューにグレードアップします。炒めものやスープにも活用できます。
甘酒
飲む点滴と言われるほど栄養価が高い甘酒は、お米を発酵させていて、腸内環境を整える作用もあります。
甘酒は、ビフィズス菌のエサとなるオリゴ糖、食物繊維と似た働きを持つレジスタントプロテインを含んでいます。また、植物性セラミド「グルコシルセラミド」には善玉菌を増やす効果があります。甘くておいしい甘酒は、食欲がない時の朝食代わりや手軽な腸活おやつにも良いです。ただしブドウ糖も含み糖質が多いので、血糖値の上昇には注意が必要です。
きゃべつ、たまねぎ、ごぼう、りんご、ぶどう、バナナ(オリゴ糖を含む野菜や果物)
オリゴ糖はビフィズス菌など大腸の善玉菌のエサになる栄養素です。これらの野菜や果物には、オリゴ糖が含まれているほか食物繊維も豊富です。
腸内環境を整える栄養素がたっぷり含まれた食材は、積極的に食事に取り入れましょう。
豆腐、きなこ、豆乳(大豆製品)
大豆にもオリゴ糖が豊富に含まれています。オリゴ糖は小腸から大腸まで届き、腸内の善玉菌を活性化してくれます。
大豆イソフラボンが大腸のエクオール産生菌に代謝されると、女性ホルモンの不足による女性特有のゆらぎに役立ちます。
大豆製品は毎食摂り入れたい食品です。豆腐は味噌汁の具や副菜として食事に、豆乳やきなこは混ぜておやつ代わりにするのもおすすめです。
チーズ
ヨーグルトほど乳酸菌は多くありませんが、チーズも乳酸菌を含む発酵食品です。 フランス料理では、消化を促すため食後に熟成したチーズを食べます。
腸内環境を整える作用を期待するなら、しっかりと発酵したパルメザンやカマンベールなどの熟成タイプを選びましょう。
プロセスチーズは、ナチュラルチーズを原料にして作られた加工食品で、加熱殺菌により乳酸菌や発酵食品に含まれる酵素が失われています。
2運動
腸内環境を悪化させる原因は、食べ物だけではありません。生活習慣や精神面も腸に大きく影響します。
気持ちが良いと思える範囲の適度な運動は、全身の血流をよくし、自律神経のバランスを整え、腸内環境を整える作用があります。
散歩やストレッチなどの軽めの運動のほか、お腹に刺激を与えるために腹筋を鍛えるのもおすすめです。ただし、激しい運動はストレスになり、腸内環境には逆効果になるため、無理のない範囲で続けられる運動を見つけましょう。
3睡眠
脳と腸は互いに影響し合う関係であることがわかっており、これを「脳腸相関」といいます。緊張やストレスでお腹の調子が悪いのは、脳と腸が深く関わっているからです。
睡眠は、脳の疲労を取るための大切な時間です。脳をしっかり休ませて機能を回復させることで、腸内環境を整えることができると考えられます。
十分な睡眠時間はもちろん、ぐっすり寝てスッキリ起きられるように寝具を見直すことも、腸内環境の改善に繋がります。
腸内環境を整えることは、免疫力のアップ・脳への影響など、私たちの体の健康につながることがわかっています。
そのためには、規則正しい生活をベースに、腸によい食品を食事で摂取し、適度な運動をし、質の良い睡眠を取りましょう。
生活習慣全体が腸に大きく影響するため、できるところから少しずつ取り入れて頂ければと思います。