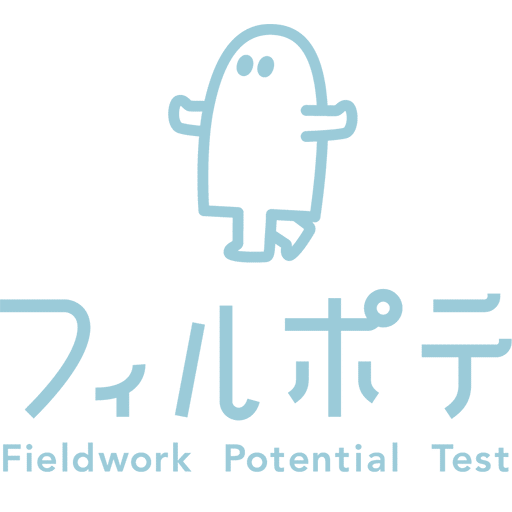編集長です。経営層が知っておかなければならない高年齢従事者の取り扱いをまとめました。令和7年4月1日から経過措置がなくなりますのでご確認ください。企業にとっては厳しい内容です。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 とは
以下、厚生労働省の令和6年12月20日のプレスリリースの文面です。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)」では、65歳までの雇用の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう、企業に義務付けています。
加えて、70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。
全ての企業に対して、課せられている義務
60歳未満の定年禁止
これは、従来から浸透している内容です
65歳までの雇用確保措置 いずれか
・65歳までの定年引上げ
・定年制の廃止
・65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
経過措置終了 何が経過措置だったのか?
経過措置は令和7年(2025年)3月31日までです。では、何が経過措置だったのでしょうか?
簡易的に説明すると、「ある一定の基準を満たしたものだけが雇用延長をできる」という規定がある企業は、「従事者が年金を受給できる年齢では雇い止めができた」という事です。令和7年3月31日までは、平成24年度に52歳、53歳になる者は年金受給開始が64歳からという根拠に基づいて64歳で雇い止めができましたが、4月からは「65歳まで働きたいと希望する従事者をすべて雇用延長しなければいけない」となり経過措置が終了します。
70歳までの努力義務
以下、厚生労働省の令和6年12月20日のプレスリリースの文面です。
70歳までの就業機会の確保を目的として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」という雇用による措置や、「業務委託契約を締結する制度の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」という雇用以外の措置のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを企業に義務付けています。
対象企業
令和3年4月1日に施行された改正点です。
・定年を 65 歳以上 70 歳未満に定めている事業主
・継続雇用制度( 70 歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
除かれるのは、定年がない企業と70歳以上も引き続き雇用制度がある企業のみです。結局のところ、すべての企業に努力義務が課されていると解釈すべきでしょう。
65歳以上の就業確保措置 いずれか
65歳以上になると、若干緩くなり選択肢が増えます。
・70歳までの定年引上げ
・定年廃止
・70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
・高年齢者が希望するときは、70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
【労働組合の過半数の同意が必要】
・高年齢者が希望するときは、 70 歳まで継続的に以下の事業に 従事できる制度 の導入
a.事業主が自ら実施する 社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
65歳までは、自社従業員として雇用し、65歳以降は業務委託という形態が選択できることになります。
業務委託となれば、社会保険や給与計算などの企業の負担も減り、発注する業務量に応じての支払いとなれば、企業は閑散期のリスクを軽減できます。
中小・零細企業はどれを選択?
待遇変更ができる雇用制度を
65歳までは雇用を続けなければいけません。そこで考えなくてはいけないのは、待遇の変更ができるようにしておくことです。簡単に言えば、会社側からの視点で、給与を下げることができる規定です。
・大企業では55歳役職定年という規定がある企業が多く、それ以降は給与を下げることができます。
・60歳定年で再雇用であれば、これまでの雇用契約とは違う雇用契約になるので、
給与を下げたり、出勤日数を調整したりが可能になります。
・雇用延長でも、規定を作っておけば、従来の○○%の給与でということや昇給しないことも可能です。
ただし、規定を作ったけれど従事者が読むことができないと問題ですので社内で公表する必要があります。
単純に定年年齢を上げると・・・
一番危険なのは、65歳定年や70歳定年にすることです。
「加齢によりパフォーマンスが落ちてきたから給与を下げる」ということで揉めるリスクがあります。給与を大幅に下げることに大変な労力と時間を要します。
法律では、雇っている側よりも雇われている側を守る発想なので、待遇(給与)の変更なしの定年の延長は特に中小・零細企業にとって存続の危機を招きます。
考えてみれば、自社がなくなってしまえば、同じ職場で働き続けることはできないのですから、「ある意味お互いのため」とも言えます。
まとめ
従事者が常時10名を超えていない中小・零細企業では、労働基準監督署に三六協定を提出するという恒例行事がないため、法改正について知る機会がなかなかありません。
しかし、法として施行される以上、守っていないと従業員から訴えられるリスクがありますので、どういう社内規定にしたら良いかを社労士さんなどに相談して設計する必要があります。
色々な法改正があります。雇用や税務や社会保険や各業界の法律など・・・
法人番号を登録しているのですから、各社に該当する法改正を都度都度メールで送ってもらうことはできないのでしょうか?
法務局への役員重任登記も10年になる前にお知らせが届けば良いと思いますが・・・